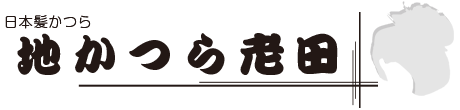修行を終え、いよいよ独立へ その1
2017/07/07
今思うと、なんだか夢の中の出来事にも感じられる修業時代は、私の二十歳の兵隊検査で終わりました。
私が入隊したのは十二月一日。しかし、十八日には、病院に入院させられていました。特にどこが悪いというのではなく、体が小さかったために体力がなかったのでしょう。同期の仲間たちの間でも一番小さく、「お前は女の子みたいだ」とからかわれたものです。その後、入院生活は半年間続き、翌年、二十一歳の五月に除隊となりました。
家に戻ってしばらくの間は、大勝さんに半月、家に半月という具合で、新派と歌舞伎の仕事をしておりました。この頃、初めて六代目菊五郎さんの頭合わせをしましたが、その時の緊張感は今でも忘れられません。
また、すぐに二代目として独立しなかったのは、私よりキャリアのある番頭さんがいたからです。番頭さんにしてみれば修行を終えたにせよ“小僧に毛が生えたくらいの若造になにができるか”と思ったことでしょう。私に対する対抗意識は、それはそれは強うものがありました。私は私で“いつか仕事で勝ってやろう”と決意したものです。後に、私がネットのかつらを考案した際に、この番頭さんが頭を下げて「ネットを分けてくれ」と私のところに来た時は、思いが果たせた気になりました。
私が家へ帰ってから一年ほど後に、この番頭さんが独立。これにあたって父は、私と番頭さんの間でお客さんの取り合いにならないよう、番頭さんには喜多村緑郎先生や河合武雄先生などの大きなお芝居を、私には、公園劇場などで行われていた沢田正二郎先生などの小さなお芝居から始めるように指導しました。
この頃になると父も体が弱ってまいりまして、そのうち、父のお客様を私が引き継ぐようになりなした。なかでも、最も印象に残っている方が伊井蓉峰先生です。当時の伊井先生の人気は絶大で、若いわたしにとってあまりにも大物でした。行くたびごとに「お父さんは名人だったよ。名人に二代なしというけれど、お前さんは名人にならなければいけないよ」と幾度となく諭されたものでした。
私は、“親の七光りで伊井先生のかつらを造っている”と言われないよう無我夢中で仕事に没頭し、なんとか伊井先生のお役に立ちたいとの一心で仕事に励んでおりました。
そのうち、座頭である伊井先生のかつらを造っているということで、岡米の名が自然に広がっていきました。伊井先生の下でお芝居をやっている方の中には、「一度でいいから岡米さんのかつらをかぶりたい」とおっしゃってくださる方も多く、とても嬉しかったことを覚えています。
 河合先生(左)と花柳章太郎先生(右)
河合先生(左)と花柳章太郎先生(右)
 ざんぎりかつらの市川猿奥翁丈 浅草のお店
ざんぎりかつらの市川猿奥翁丈 浅草のお店
 河合武雄先生
河合武雄先生